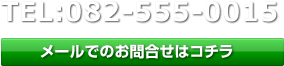6月12日(水)、佐東公民館で広島市「小規模修繕制度」について、安佐南北登録者連絡会が交流会を開催しました。
参加者は登録業者が8名と会外業者1名、要求運動部員2名、事務局員2名の他、日本共産党で県議会の藤井敏子県議と、広島市議会の清水てい子市議、中村たかえ市議の3名にも参加いただき、合計14名の参加でした。
現在(令和5~7年度登録)の安佐南北の登録業者は55名です。
交流会に参加された登録業者の皆さんから、受注状況などの様子を話してもらいました。
《登録業者から報告》
1.「以前は児童館などのトイレを和式から洋式へ交換する依頼などがあったが、5年位受注をしていない。教育委員会も何もない。」
2.「安佐北区の地域おこし、農林課からの受注がたくさんあった。水道、タイル、内装、その他を含む。」
3.「7年位前まではあったが、その後は無い。70万円位はしたと思う。」
4.「最近は無い。以前5万円位はした。」
5.会外の業者の方は「初参加なのでよく分からない。」など、報告していただきました。
工事の発注状況は、コロナ以前は順調に伸びていましたが、コロナ後はぐっと落ち込んでいます。また、コロナ過で区役所や市役所等、行政との懇談ができなかった時期もありました。
受注減少の原因と今後の対策
《受注減少の原因》
1.コロナ過で行政との懇談ができなかった。
2.学校ごとの発注だったものが、区ごとに取りまとめる学校事務センターができたのも要因かと思われます。その中で、安佐北区は若干ではありますが受注が伸びました。
3.学校では用務員さんがいて、できるものは修繕しているものと思われるし、PTAの地元の業者に発注しているのもあると思われます。
《今後の対策》
1.この交流会での意見を参考に、各区役所との懇談が必要です。
また、登録業者の更新時期までに、広島市契約部とも懇談して、2.相見積りの5万円を10万円以上にしてもらうことや、
3.受注上限金額を50万円から100万円以上に上げてもらうこと、
4.教育委員会との懇談で、発注割合が少なすぎることを訴える必要もあります。小規模修繕に該当する工事のうち、金額、件数とも10%しか登録業者に発注されていないためです。教育委員会はそもそもが少なすぎるので、50%は目指したい。
5,市議会の令和4年12月議会の一般質問で藤井市議(当時。現在は広島県議)が、ここ数年低い数字で推移していることを質問しています。
6.また、市議会の令和6年2月定例会では清水てい子議員が同様の質問をしました。
7.広島市(施設課長)の回答は、学校施設の老巧化で修繕の金額が大きくなっているので受注件数が減っているのではないか、と回答しています。
《今後の提案》
1.広島市の小規模修繕契約希望者登録制度は、広島市全体での制度であるので、広島市内の各民商と相談し、登録業者を増やすことが必要と思われます。
2,また、広島市との懇談も、市内4民商での懇談が望まれています。
カテゴリー: 広島北
高すぎて払えないと悲鳴が 3人家族で年間所得の19%にも!
広島市が令和6年度の国民健康保険の保険料率を発表しました。(図1)
昨年に続き今年も、1項目を除き値上げされ、昨年と所得が同じ場合は全ての世帯が値上がりすることになります。限度額も106万円に値上がりしました。

所得に関係なくかかる人数や世帯にかかる「均等割」と「世帯割」が上がり、低所得世帯にとって厳しい負担増となっています。
広島市の公表する「国保料の目安」によると(収入・生活費に占める負担が重い国保料。図2)、
年間所得に対する国保料の金額は、1人世帯では所得額の15.3%に、3人家族(40歳以上2人含む)世帯では所得額の19.1%(前年は17.4%)を占める事になります。
いずれの家族構成でも、低所得世帯ほど、家計に占める国保料の割合が高くなっています。
所得が高いほど納税額が増える所得税などと逆行し、逆進性の高い状態となっています。

滞納は放置せず民商へ相談を
毎週木曜日の「陽気な道場」にも、国保料を含む税金が高くて払えないという相談が相次いでいます。
払えないからと放置せず、支部や民商事務局へ、まずは相談しましょう。
また、広島北民商も加盟する広島市社会保障推進協議会でも、広島市に対し国保行政改善の交渉をおこなっています。
婦人部学習レクリエーション『大洲雨水貯留池見学』
5月28日(火)、婦人部の毎年恒例の学習企画で、今年はマツダスタジアム地下にある「大洲雨水貯留池」の見学ツアーに行きました。婦人部員7名と男性2名、広島県婦協からも2名が参加され、11名での参加でした。
これまでの学習企画は平和学習が多かったのですが、近年は毎年のように豪雨災害が頻発していることもあり、自分たちが住んでいる広島市の対策に注目し、自分たちの目で見て学習しようと企画されました。マツダスタジアムの地下でひっそりと広島市民を守っているのが、「大洲雨水貯留池」です。
大雨が降った時に浸水被害を防ぐために作られた施設で、直径100m、高さ5.4m、貯水量1万5千3m、平成21年の球場オープンと同時に使用が開始された貯留地ですが、過去3回ほど満水に。西日本豪雨の時も機能し、大洲地区は大きな被害が出ずに済みました。
ひんやりと涼しい地下空間は、普段は無人の施設。グラウンドに丸々収まるほどの大きさで、2つの雨水貯留地が管理されています。大洲雨水貯留池には雨水を貯めるだけでなく、もう一つ「雨水の再利用」という役割があります。スタジアムではグラウンドへの散水やトイレの水も雨水が再利用されています。球場周辺のせせらぎ水路にも活用されています。
見学ツアーは1時間半ほどで終了し、参加者には「カープ坊やをあしらったマンホール」を紹介したマンホールカードのプレゼントがありました。
次週も引き続き、参加された皆さんの感想などをご紹介します。
広島北税務署に申し入れと交渉
不平等な減税策や、収受印廃止、インボイスへの抗議と改善要望
広島北民商は5月22日(水)、3・13行動の一環として広島北税務署に対し申し入れと交渉をおこないました。北民商から久村会長、税対部から竹本部長、大下さん、山下さん、婦人部から中島部長、樫本さん、片山さん、事務局3名の計10名での交渉となりました。
税務署からは大谷総務課長ら2名が応対しました。
税務署への申入れ事項と税務署の回答や質疑は下記の通りです。
【税務署への申入れ事項(要旨)】
①3・13集団申告が双方スムーズ に進む体制を整えること。
②令和7年からの申告書等への収 受印廃止を撤回すること。申告 内容の証明を負担なくできるよ うにすること。
③消費税率を5%に引下げること。
④インボイス制度は廃止すること。
⑤税務相談停止命令制度は廃止す ること。国会答弁に従い、対象者を恣意的に広げないこと。
⑥負担を強いる税務調査や呼び出 し等はおこなわないこと。理解 と協力を得る立場で進めること。
⑦納税緩和措置を周知し、強権的・ 機械的徴収をおこなわないこと。
⑧憲法に基づく国民の権利を守り、 税務運営方針を遵守すること。
⑨広島国税局及び国税庁にも要望 を伝え、改善を求めること。
【定額減税について】
①すべての事業専従者を定額減税 の対象に加えること。
②対象とならない場合に給付金を 支給すること
今回も、税制や法律の廃止は「回答する立場にない。上級官庁に伝える」とした上で、具体的な話に入りました。②収受印廃止について、総務課長は「これまでは納税者の要望に応え押印してきた。デジタル化に向け、周知期間を設け説明していく」と答えました。まだ確定していないことも多く、改めて押印の継続を要望。押印廃止の場合の証明方法への不安も訴えました。
④インボイスについては、周知が不十分な中で多くの無申告者や特例未使用といった業者も出ています。無申告者に対し特例の案内も含め丁寧に説明するよう求めました。
⑤税務相談停止命令制度については、税務署内での動きを聞くと、税理士法改正についての研修があった」との回答でした。その上で、対象となる行為等を答えましたが、参加者からは世間話や一般情報の伝え方によっても恣意的(わざと)に対象にできてしまうあいまいな部分への不安の声が次々出され、改めて、納税者同士の教え合う活動への不当な介入をしないことを求めました。
専従者の定額減税対象外に、婦人部からも抗議
今年の6月からの定額減税で、白色専従者等が減税や給付金の対象にならない問題について、長年にわたり所得税法56条廃止の運動を続ける婦人部から、中島婦人部長らが改善を求めました。中島部長、樫本副部長らは、「私たち専従者がなぜ該当しないのか」「事務の煩雑さも含め、納税者への押し付けや差別はやめて」と訴え、所得税法56条で苦しめられる状況に怒りの声が上がりました。(※全国商工新聞5月13日号1面)
税務調査でこの間起きている問題についても追及しました。県外出張が続く中でも日程調整に協力している納税者が、担当署員の希望日程が合わず「非協力的だ」と言われた問題で、竹本部長も強権的な署員の対応に強く抗議しました。総務課長は「実際に発言があれば、問題であり指導する」と答え、事務運営指針等を順守することも回答しています。
最後に、「税務署が調査や徴収で『適正な課税』を強調する様に、納税者にとっても各種控除や決算内容に漏れやミスが無い『適正な課税』の申告にしたい」と訴え、この日の交渉を終えました。
市収納対策部へ申し入れと交渉
実態つかまず、制度活用もせず 不当な徴収・滞納整理が横行
5月2日(木)、広島北民商を含む市内4民商が合同で、広島市財政局・収納対策部へ申し入れと交渉をおこないました。北民商から久村会長、横畑副会長、寺本要求運動部長、事務局3名の計6名が参加し、4民商から17名と、広島法律事務所の井上弁護士も同席しました。
広島市からは特別滞納整理課の山本課長、徴収企画課の今井課長ら7名が出席しました。
事前に要請していたデータ資料も有り、状況の説明なども交えて回答がありましたが、実際に現場で起きている対応とはかけ離れた回答ばかりで、参加者からは抗議の声が相次ぐ交渉となりました。
要請への回答では、特別滞納整理課の扱う「高額滞納分」の範囲について、令和6年度は、市税等で60万円以上、国保で50万円以上、あるいは附帯金(延滞金等)のみで50万円以上の滞納金額の事案を取り扱っているとの回答でした。
国保料は毎年値上がりし、国保料の世帯当たりの上限額は104万円にもなります。市の試算でも子供2人を育てる4人世帯で年間所得316万円以上は50万円の国保料が発生します。
1年で発生する額が「高額滞納」扱いになるという線引きは厳しすぎます。令和4年度の滞納状況は市税で3万人、国保で2万人に上り、差押えも7658件おこなっています。
会員さんなどから相談があった事例を基に「介護や生活、休業などの実情がまるで聞き入れてもらえていない」状況を抗議し、実際の事例として、破産手続き中の滞納者への「破産したら滞納税金の支払いに充てられるだろう」と法の趣旨に反した対応や、収支や生活費を考慮しない売掛金の全額差押え、「借入返済を止めれば払えるでしょう」といった発言など、現場では強権的な滞納処分が横行しています。
これらの実態に対し、山本課長からは「挙証」という言葉も思わず出されながら、その上で「実態を確度(=正確さ)を持って説明してもらえれば」と発言。
今井課長も「真にやむを得ない事情について、言ってもらわないと分からない」と発言するなど、まるで事情を説明ができない納税者が悪いと言わんばかりの回答でした。
「相談してくれと言うが、実際は厳しい対応が多く、敷居が高すぎる」、ハードルを上げているつもりがないとの回答に「徴収職員は相談のハードルが高いという事を自覚しなければいけない」といった抗議の声が相次ぎました。
これらの要請に対し、「生活の実態を丁寧に伺い、個々の事情を十分調査し、適切に対応すること」との対応方針に変わりがない事や、差押え禁止財産や差押える財産の選択なども国税徴収法や国会答弁等に従い、職員の会議でも周知する事なども確認しました。
交渉後、参加者からは「改めて、毎年のように交渉に来る必要があると感じた」といった感想が出されました。

県婦人部協議会 一泊学習会
30名の参加で、記帳や健康講座、婦人部活動などで楽しく交流
4月13日(土)から14日(日)にかけて、県婦協が一泊学習会を開催し、『尾道ふれあいの里』で県内7民商30名、北民商婦人部から5名が参加しました。
初めに主催者あいさつで県婦協の島会長が「集まっての学習会は久しぶり。大いに学び合い、交流を深めましょう!」と参加者に元気に呼びかけました。
昨年改定された新しい「婦人部活動の手引き」を使い、3人のパネリストが手引きの内容と自分たちの商売や活動について話をされました。パネリストを務めた北民商婦人部長の中島さんは、ご主人と事業を始めたきっかけや民商に入ってからの経験などを話され、西部民商の隅田さん、広島民商の本田さんとともに、所得税法56条廃止の運動や記帳カフェなど、婦人部で取り組んでいる内容についても意見を出し合いました。
全婦協総会方針の学習では、島県婦協会長が解説し、参加者と読み合わせもしながら各婦人部の活動も交えて進行しました。
民商・全商連の基本方向は広島県連の坂井副会長が担当し、限られた時間ながら各章ごとに読み込んだ内容を補足して説明していただきました。その後、参加者の自己紹介。宿泊で参加された方々は夜の交流会でもカラオケや「確定申告ゲーム」をしながら、楽しく大笑いしながらの交流となりました。
2日目は様々な内容でおこなわれました。
初級レベルの記帳学習を広島の遠地事務局員が担当し、簿記の基本や弥生会計の使い方について、参加者の例題も使って、笑いも交えながら学習しました。
SNS活用講座は広島県連の寺田事務局長から、三原民商会員さんの経験を紹介していただきました。
最後の企画は健康講座「歌って鳴らして体を動かそう!」。府中市の音楽療法士・木村さんが講師で「歌う事は誤嚥を予防する効果があります」と、参加者全員で「てんとう虫のサンバ」、「サザエさんのテーマ」などの楽しい音楽に合わせ、子供から大人まで歌いながら体を動かし、世界の珍しい楽器を使っての合奏もしました。
今回の一泊学習会では、2日間にわたりみなさん学習の時は集中して学習し、意見交換の時は積極的に話をして、交流時はたくさん笑いながら楽しく交流できました。

社会保険料 徴収対策交流会
4月9日(火)、全商連主催「社会保険料・徴収対策交流会」が全国250ヶ所を結ぶオンラインで開かれ、広島北民商からも、久村会長、寺本要求運動部長ら9名が、民商事務所など2ヶ所から参加しました。まず初めに、日本共産党の小池晃参議院議員から、国会(財政金融委員会)での答弁の概要の説明がありました。
強権的徴収が横行する背景 社会保険料の強権的徴収やめよ
税金や社会保険料の滞納徴収について、財政金融委員会での答弁は、
①給付困難な場合は、換価の猶予も最長4年間認められる。
②差し押さえる財産は、国税徴収法基本通達の47の17を適用して柔軟に対応している。
③納付計画が不履行になった場合も、見直し協議をして変動型の分割納付も可能と、それぞれの回答が有りました。
それぞれについての担当者の答弁は、国税庁からは猶予制度について「期間は通常1年間。ただしやむを得ない場合は2年間、又は納税者が換価の猶予を申請する場合や、行政側が職権で猶予をする場合は、それぞれで合計4年間の猶予が出来る」と説明。
財務大臣から「税を払って下さる方を破綻にまで追い込んで税を取ろうということは、妥当性に欠ける」と回答があり、厚生労働省からは「個々の事業者の状況をお聞きし、適切に対応する様に、日本年金機構に指導していく」と回答が。
これら小池議員の国会での論戦の一方で、実際の現場では徴収担当者の強権的な対応が問題となっていて、参加した各地の民商から、以下の様な事例が報告されました。
例えば、
①一括納付か差押の2択か、3ケ月又は1年以内の無理な納付計画を作成させられる。
②納付協議中に差し押さえをする。
③売掛金を差し押さえる。
④事業所の内規通リやっている。
⑤法律を無視し、国税よりも優先して徴収しようとする。
⑥事業が継続できなくても仕方がないという態度。
以上のように現場では強権的な徴収がおこなわれています。
加入強化で起きている問題
そもそも社会保険は半ば強制的に加入させられ、高い保険料が問題であり、払えなくなる状況が必然的に起こる保険料です。全国の各民商には不当な徴収相談が寄せられており、コロナ後に体力がまだ戻っていないため、納付が困難な事業主は今後も増加していくだろうと思います。
さらに、社会保険料の未納が有れば融資が困難になる可能性もあります。
令和6年3月の企業倒産は906件で、前年同月比11.99%増加している事からも、大きな影響が出ている事が分かります。
北広島町、安芸太田町と業者支援について懇談
【要望】
①物価高騰対策として、直接支援等の中小業者支援を実施してほしい
②インボイス廃止の意見書を国に上げてほしい
年度末を迎える3月28日(木)、29日(金)の両日、広島北民商は全自治体懇談の一環として
北広島町、安芸太田町と相次いで懇談しました。
北広島町懇談 インボイスの影響、農家や組合にも
28日の北広島町との懇談は広島北民商から久村会長、横畑副会長(県連副会長)、小田北広島支部長、陶山事務局長の4名が訪問し、川手総務課長、国吉財政政策課長、中川商工観光課長の3名に応対していただきました。初めに久村会長が申し入れをおこない、要望内容について懇談をおこないました。
物価高騰対策については、この間、燃料費等への補助金制度を独自におこなってきた事が紹介され、引き続き財源のできる範囲で取り組んでいきたいと話されました。
インボイス制度については、令和3年12月議会で、日本共産党の美濃町議の尽力もあり、国に対し「インボイス制度の実施延期を求める意見書」が全員一致で採択されていますが、今回の懇談で町からは「当時、制度の準備や周知が間に合わない状況で議会・委員会の判断があった。制度開始後は農家やシルバー人材センターなどで影響が出ていると認識している」との回答があり、横畑副会長も「私たちのような免税業者の多くも、仕事を続けるために登録をした。建設業も景気が良ければ働いただけ儲けにもなっていたが、今は負担ばかり増え、若い業者は社員になった方が楽という人も増えている。この上、インボイス制度で廃業が増えることになる」と実情を訴えました。小田支部長からは、農事組合法人が労務費の支払方法の違いによって大きな負担を負う事例が出ている状況なども説明がありました。
要望書の他に、国保の県単位化の問題も話題に上がると、「町では子ども医療費助成は入院・通院とも18歳まで(県内でトップタイ)。国の少子化対策にも期待しつつ、県単位化後も後退させないようにしたい」といった点なども話ができました。
安芸太田町懇談 独自の景気対策。保険料負担不安も
続く29日(金)には安芸太田町と懇談しました。二見企画課長、沖野税務兼会計課長、産業観光課の渡海観光係長の3名に応対していただきました。
安芸太田町でも価格高騰対策の補助金制度を実施するとともに、経済対策として地域通貨『モリカ』の活用を進めており、昨年10月からのキャンペーンでは町内で5千万円以上の消費=経済効果につながっていることも紹介されました。
インボイスの話題では、中小業者の実情を訴えた上で、町からは「制度開始以前から町内の業者は厳しい経営状況が続いている。インボイスについては、取引で不当な取り扱いが無いように周知するなどしていきたい」と話されました。
国保については町財政で負担軽減をしてきたものの、県統一保険料となっている後期高齢者保険では「4月からの負担増で、多くの声が寄せられている。高齢者の多い町としては大変」と話され、国保も統一保険料になると大変になる状況がうかがえる話でした。
今回は、年度末で3月議会終了間もない時期で、安芸太田町は町長選挙も控えるタイミングでしたが、両町とも諸問題について意見交換ができました。
いのちと健康を守る学習交流会
6年ぶり開催で、国保改善運動など学び合う
3月24日(日)、広島県連共済会主催で「いのちと健康を守る学習交流会」がおこなわれました。
10民商42名の参加があり、北民商共済会からは伊村理事長、横畑副理事長、礒邊副理事長、渡辺理事(川内)、礒道事務局員の5名が参加しました。会場は湯来ロッジ周辺で、午前中は湯来交流体験センター内で「国保改善運動」についての講演を聴講しました。
開会あいさつで平野県共済会理事長から「前回の宮島(北民商共済会担当で開催)での交流会から5年ぶりの開催。やはりコロナ禍の影響は大きかったと感じる。本日学習する『国保制度』は、低所得者ほど負担が大きく、無保険が原因で治療を受けないで亡くなる人も増えている。私たちの生活や命にも関わってくるものなのでしっかり勉強しましょう」と話がありました。
今回の講師は、千葉県社会保障推進協議会(社保協)・国保責任者の鈴木英雄さんが務められました。千葉県には県社保協の他、準備会も含めれば18の地域に社保協があり、ともに国保改善の運動にとりくんでいます。また鈴木さんは元々、民商や千葉県連で事務局員として働いていたそうですが、2015年に千葉県銚子市で起きた県営住宅追い出し母子心中事件の調査に志願して参加したことがきっかけで、社保協で国保問題に取り組むようになったそうです。
安心して医療を受けるためには、社会保障としての国保制度が大切ですが、新しくできた法律などでは、この「社会保障」の文言が使われなくなり、その代わりのように「自助と連帯の精神に~」とか、「国民の共同連帯の~」など、住民・国民の相互扶助にすり替わっているという話や、国保の運営方針が非情な効率化を進めさせているといった話をされました。
役員23名が地域で会員訪問 ポスター貼りや署名も
炊き出しで楽しく元気な行動に
1月21日(日)、今年の春の運動で最初の拡大行動として、会員訪問にとりくみました。
参加は役員23名と事務局の計26名。支部長さんが5名、婦人部役員さん8名、共済役員さん6名など、各支部から多くの参加があり、元気が出る取り組みとなりました。伊村組織教宣部長がこの日の行動内容を説明し、2~3名ずつのグループを作って訪問先を分担しました。
今回は確定申告の時期に向けて、インボイスで困っている人などを民商に紹介してもらい、仲間を増やすための声かけをみんなでおこなう事に。
訪問先ではインボイスの相談や署名のお願いもして、広島ドラゴンフライズの朝山選手が登場する新しいポスターの貼り出しもお願いしました。
仲間同士交流し、紹介も広げ
この日一日で97件のお宅を訪問し、57名とお話をすることができました。訪問先の飲食店でポスターを広げていると、居合わせたお客さんが「この人知っているよ」と反応もあり、「見てもらって関心を持ってもらえれば」と早速手応えを感じた組もありました。また、インボイスの事では訪問先でも対話になり、対応に困っているといった声も聞かれました。署名にも協力いただき、1日で74名分の署名が寄せられました。震災義援金を託していただいた方もいました。

お昼は事務所に一度帰って、婦人部の片山さん、田村さんに炊き出ししていただいたご飯をいただきました。
暖かく美味しいご飯を用意していただき、参加者同士の交流にも花が咲き、午後からの行動にも元気に出発することができました。
仲間を増やす運動では、相田・西支部の会員さんが、独立して頑張っている息子さんにも民商で相談をと入会してもらうことになりました。
可部北支部の山下さんは、元会員さんに商工新聞を読んでもらうなど2名の読者をふやし、婦人部員も2名の会員さんにお願いして入ってもらうなどの成果となりました。
他にも2名の読者がふえ、仲間を増やす運動では、入会1名、読者4名、婦人2名の成果となりました。
これから確定申告の時期に入り、インボイス登録で不本意ながら消費税申告が必要になる方も沢山いる一方、全国30万人以上が相談先が無いとも言われています。「インボイスの事なら民商がチカラになります!」と、周りの業者仲間にもぜひ民商をご紹介ください。