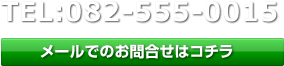定額減税で過大な事務負担民商で給与明細を作成
6月給付分の給与から始まった『定額減税』が、給与明細への記載を必要とし、多くの会員が相談に訪れています。帝国データバンクのアンケートによると、66・8%の企業が「負担を感じる」と回答し、会計ソフトの改修費用など余計な出費が発生していると訴える企業が大多数を占めています。
民商は会員の負担を軽減するため、専用のPCソフトを導入。無料で利用でき、多くの会員から好評を得ています。利用希望者は予約の上、民商事務所までお越し下さい。
負担増えるばかり平山さん=東2・鉄鋼=
「政府が急に押し付けてきたことで、事務仕事が増えてしまい、本当に腹立たしい思いです。こんな面倒なことをするなら消費税を減税して欲しい」と不満を述べました。
橘高さん=西・鉄筋=
「減税のことだけ言って、実際には森林環境税という新たな税金ができたり、復興所得税は2037年まで13年間も延長された。結局払う方が増えている」と怒りの声をあげました。
野上さん=東2・飲食店=
「ソフトを使えば、月に一回パソコンを操作するだけで減税額の管理もできるし、7月の半期特例や年末調整もすぐにできる。非常に便利です」と述べました。
国民の声で減税定額減税は負担が大きく効果が薄いものの、国民の世論と声で政府に減税策を実行させたことは、消費税引き下げへの大きな一歩となりました。これは、政府が国民の声に耳を傾け、政策を変えることができることを示しています。中小事業者の営業と暮らしを守るためには、今後も「消費税引き下げ」の声を強く上げ続けることが大切です。継続して声を上げることで、政府への働きかけを強め、消費税引き下げを実現させましょう。今後も消費税引き下げの実現を目指して運動を続けていきましょう。