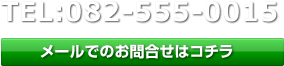インボイス、電帳法、命令制度、定額減税と目白押し!
5月8日に三次民商税対部は、『3・13重税反対全国統一行動』の時に申し入れた内容について三次、吉田両税務署に交渉を行いました。三次税務署は金子総務課長、緒方係長が、吉田税務署は金光総務課長が対応し、国重会長、植野税対部長をはじめ三次が6名、吉田が4名が参加しました。
税務相談停止命令制度について
4月から始まった税務相談停止命令制度。税務署の回答としては「集まって学び合うことについては該当はしない。だが脱税指南など重大かつ緊急な案件なら当てはまるかもしれない」ですが、4月になり、税務署として何か変わったことがあるかというと「特段、何か変わったことはありません。停止命令制度に抵触する案件が生じたら分かってくるのではないか」とのことでした。
自主計算運動では保険料控除の計算を手伝うのはどうなのかを聞くと「ギリギリ抵触する可能性があります」と回答。それでは国税庁のパンフレットを使って手伝うのはどうなのかと問うと「それは該当しないと思います」との回答を受けました。国税庁ホームページには税法の説明を解説しているので今後も利用していくことが大事です。
電子帳簿法について
1月から始まった改正電子帳簿法はネットで取引をしている全事業者が対象ですが、全く周知されていないのが現状です。この間、参加者がクレジット会社が電子帳簿法に対応していない場合についての対応について国税庁に問い合わせたところ、はじめに答えた人は「今まで通り、紙媒体での保存で大丈夫です。深く考えなくても良い」と言い、納得できない参加者は後日、もう一度国税庁に聞いたところ、別の人が出て「保存できるデータは電子で、どうしても対応していないものは電子と紙媒体で整理を」と回答。ただでさえ複雑で分からない制度なのに、国税庁の回答も変わると納税は混乱すると訴えると「周知を徹底するように個別で学習を受け付けている。ただ税務調査の時、電子帳簿法に沿ってなかったとしてすぐに金銭が動いてないということに繋がるということはないと思う」との回答でした。
インボイス制度について
制度が始まって初めての申告をむかえて混乱など起きているか聞いてみると「それなりの態勢を整えていたので混乱は起きなかった。申告者数が増えているので、申告漏れはそんなにいないのでないか」との回答でした。
収受印について
この問題は、税務署はデジタル化に向け利便性かつ効率的にみて判断したと言っていますが、それに伴い納税者に担保されているかというと、今から周知徹底ということで全く利便性が感じられないと訴えました。
税務調査について
「適正な納税を期するために調査は行われなければならない。だがこの間、税務署には裏金問題で抗議が多数寄せられている」との回答でした。
要望項目
①納税の義務は本人の自由なのか教えてください。
②インボイス制度を廃止し、消費税率5%へ引き下げるよう、上級官庁へ伝え、その回答を教えてください。
③1月から始まった電子帳簿法は、国税庁の回答が統一しておらず、様々な情報が散乱し中小業者は何を信じていいかわからない状況です。税務調査だけにあるこのような制度は即刻、廃止してください。
④税務相談停止命令制度は脱税や不正還付の指南など、悪質なものに限定し、納税者が教え合い、自らが所得税や納税額を決める民商の自主計算運動を対象とすることのないよう周知・徹底してください。
⑤来年度から確定申告書に収受印を押さないことを公表しましたが、全部押さないことではなく、希望者には押印の継続をするなど、臨機応変な対応をしてください。また納税者には確定申告書、納付書を送ってください。
⑥不要・不急な税務調査は厳に慎み、法的な根拠のない質問応答記録書を強要しないでください。
⑦納付困難な納税者には真摯に対応し、実情に沿った納税緩和措置の活用を図ってください。
⑧すべての税務署員が憲法順守し、税務運営方針を守ることを徹底すること。